老子は周の時代に生きたとされる諸子百家の1人で、同時代を生きた孔子や荘子と並んで、中国を代表する思想家としてとらえられています。しかし、その生涯は謎に包まれており、本当に老子という人物がいたのか、老子は200歳まで生きたのではないか、著書「老子道徳経」は複数の人物による共編ではないかという様々な意見が飛び交っているのです。

老子は「道(タオ)」や「無為自然」を説きながら人生を全うし、「老子道徳経」の中において、「大器晩成」、「千里の道も一歩から」などの有名なことわざの語源ともなる言葉を残しました。そして、誰もその存在を確信できるものはいないにも関わらず、老子の教えを元に「道教」という宗教が成り立つことにもなるのでした。
老子は世間に注目されることを嫌い、庶民に紛れながら教えを説いていったとされていますが、諸子百家の書物「荘子」や「荀子」にもその名前が登場することから、その教えはのちの思想家たちにも影響を与えていたことがわかります。
今回は謎多き老子の生涯を詳しく調べてみたいと思った筆者が、様々な文献を読み漁った結果得た知識を元に、老子の生涯、名言、孔子や荘子との関係性についてなど幅広く紹介していきます。
この記事を書いた人
一橋大卒 歴史学専攻
Rekisiru編集部、京藤 一葉(きょうとういちよう)。一橋大学にて大学院含め6年間歴史学を研究。専攻は世界史の近代〜現代。卒業後は出版業界に就職。世界史・日本史含め多岐に渡る編集業務に従事。その後、結婚を境に地方移住し、現在はWebメディアで編集者に従事。
老子とはどんな人物か
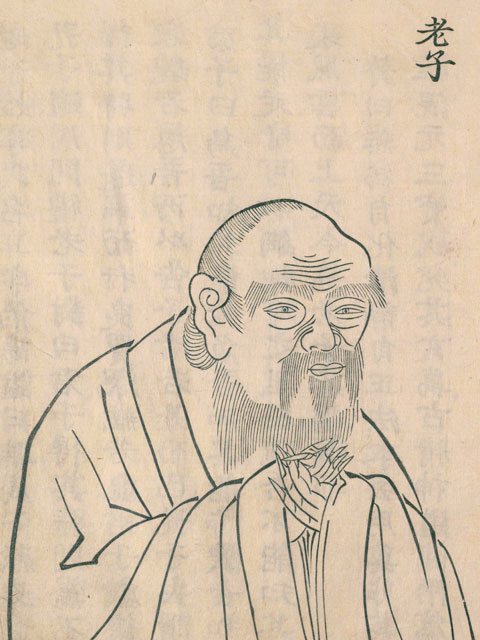
| 名前 | 老子(姓:李(り)、名:耳(じ)、本名:李耳(りじ)、元服してからの字(あざな):伯陽(はくよう)、死後の諡(おくりな):聃(たん)) |
|---|---|
| 誕生日 | 不明(紀元前550年代、紀元前400年代など確かな月日は定まっていない) |
| 没日 | 不明 |
| 生地 | 楚の国・苦県・厲郷の曲仁里(現在の河南省周口市鹿邑県) |
| 没地 | 不明 |
| 宗教 | 道教 |
| 経典 | 老子道徳経 |
| 学派 | 老荘思想、道家 |
| 思想 | 道(タオ)、無為自然 |
| 配偶者 | 不明 |
| 埋葬場所 | 不明 |
老子の生涯をハイライト

老子の生涯をダイジェストすると以下のようになります(司馬遷の「史記」参照)。
- 紀元前550年前後に老子が誕生、孔子(紀元前552年誕生)よりも数年早いとされる
- 老子は図書室の役人を生業としていた
- ある日、孔子が老子を訪ね「礼」について質問をしようとするも、老子は孔子の態度を罵って、追い返す
- 周に先の未来が見えないことを嘆き、周を去ることを決意
- 周から立ち去る際に通った関所において、関所守りの長官・尹喜と出会う
- 尹喜に「ぜひ私のために書物を書いてください」と依頼され、上下二巻に渡る書を執筆、「老子道徳経」と名付ける
- 「老子道徳経」を書き終え、関所を後にする、その消息を知る人は誰1人としてない
- (老子が200歳まで生きたとする場合)紀元前350年頃、秦国のトップと面会し、「約600年後に天下統一を成し遂げる人物が現れる」と予言
数々の思想を紹介!(女性原理の哲学、水の思想、赤子の思想など)

女性原理の哲学
「男性の剛強さの限界を知り、女性の柔和さを守りつづければ、やがて天下の水を集める谷となることができよう。」
老子の中では「柔弱の徳」と呼ばれていますが、処世術の中でもっとも尊重すべき考え方が、柔弱の精神を持ち、自らを低きに起き、周りと調和する精神を持つことなのです。女性は柔弱の精神を持っていることから「無為自然」の状態に近いと老子は説いているのです。

「天下には始めがあり、これを天下の母とよぶ。この母を体得した上で、その子である万物を知り、その子を知ったあとでふたたび母に帰ってこれを大切に守るようにすれば、一生その身を安らかにすることができよう。」
女性は柔弱の理想形となるばかりではなく、万物の根源でもある「母」にもなる、そして、その思想は「道(後述)」にも繋がっていくと述べられています。
老子は、女性のようにしなやかに生きることで永続的に「無為自然」を遂行できると述べており、男性のような剛強の精神では、世間から賞賛を得られるかもしれませんが、長続きはしないということを説いたのでした。これが女性原理の哲学です。
水の思想
「天下に水より柔弱なるはなし。しかも堅強なる者を攻むるに、これによく勝る者なし。その以てこれを易うるなきを以てなり。弱の強に勝ち、柔の剛に勝つは、天下知らざるはなきも、よく行うとことなし。」

水はどのような器にもおさまるように、相手によってその姿を変化させ、柔軟に存在している、これほど柔弱なものは他に類を見ない、と老子は述べています。その一方で「雨垂れ石を穿つ」というように、岩を突き通すような威力を発揮することもあるため、老子の哲学の中では「水」が「女性」と並んで、生き方の参考にすべきものであるとしました。
赤子の思想
「精気を純粋に保ち、柔和の徳をきわめ、嬰児のようでありたいものだ」

人間の中で柔弱の最たるものは嬰児(赤子)であると老子は述べています。赤子は生まれたばかりのため、人間のうちで最も無為自然に近い、そして、自然の徳を備えた人間ほど赤子と比較されるようになると考えました。
老子・荘子・孔子について簡潔に説明

老子は「老子道徳経」を執筆し、「道教」の始祖として信仰されている人物ですが、その実体は謎に包まれています。荘子は紀元前300年前後に活躍し、「荘子」を執筆した思想家で、老子とともに「道教」の始祖として知られていますが、荘子の生涯もベールに包まれており、詳しいことはほとんど分かっていません。
孔子は唯一、生涯に関する資料が多く残されている人物で、弟子たちによってまとめられた孔子の言語録が「論語」として出版され、現在に至るまで多くの人々に愛される書物となりました。
孔子は人々が「仁(人道的人間愛)」を身につけ、「礼(家父長制を主とする身分制度)」に従うことによって理想的な社会が成り立つと説き、老子と荘子は「老荘思想」として「無為自然」という思想を掲げました。
道教の経典「老子道徳経」とは?

「老子道徳経」とは春秋戦国時代の諸子百家の1人である老子が書いた書物とされており、同じく諸子百家の1人である荘子の書いた「荘子」とともに道家の代表的書物として数えられています。上下二編に分かれており、全部合わせて八十一の章が収められました。

「老子道徳経」は孔子の思想が根幹となっている儒教に関して、これを批判する形で書かれており、「仁義、善、忠誠、知恵などはそれらが現実に少なすぎるからもてはやされるのであって、道の存在する理想的世界においては必要のない思想である。」と一蹴しています。
この「老子道徳経」の思想が、のちの「荘子」や「淮南子」などに影響を与え、「道教」の信仰として確立するようになるのでした。老荘思想は中国だけでなく、日本などのアジア圏へと広まり、19世紀以降にはヨーロッパの各国語に翻訳されるなど、いまだに多くの人々に影響を与えているのです。
![レキシル[Rekisiru]](https://rekisiru.com/wp-content/uploads/2021/04/Rekisiru_Logo_v3-1.png)