「アーリマン(アンリマユ)ってなに?」
「アーリマンってどんな神なの?」
「ゾロアスター教ってどんな宗教?」
あなたはこのような疑問を抱いているのではないでしょうか。アーリマンとは、ゾロアスター教と呼ばれる宗教の創世神話に登場する神の一柱です。日本では一般的に”アーリマン”という名前は定着していませんが、『アンリマユ』と言えば少しピンとくる方もいるのではないでしょうか。

アーリマンは人間に加護や繁栄をもたらす神ではありません。ゾロアスター教の神話におけるアーリマンは、人間にとって一般に”悪”や”苦痛”とされるもの全てを司る存在とされ、宗教全体から明確に敵意を向けられる存在として登場しているのです。
ということでこの記事では、一般的にアンリマユと呼称されることの多い、ゾロアスター教の絶対的な悪神『アーリマン』について解説していきます。
この記事を書いた人
Webライター
フリーライター、mizuumi(ミズウミ)。大学にて日本史や世界史を中心に、哲学史や法史など幅広い分野の歴史を4年間学ぶ。卒業後は図書館での勤務経験を経てフリーライターへ。独学期間も含めると歴史を学んだ期間は20年にも及ぶ。現在はシナリオライターとしても活動し、歴史を扱うゲームの監修などにも従事。
アーリマン(アンリマユ)とはどんな存在か
| 名前 | アーリマン アンリマユ アンラ・マンユ |
|---|---|
| 登場神話 | ゾロアスター教創世神話 (アヴェスター) |
| 誕生 | 世界の始まりよりも前 |
| 死没 | 現在も生存しているとされる |
| 生地 | 不明 |
| 現在の所在地 | 深闇 |
| 司るもの | 悪、創造 |
| 配下 | ダエーワ、アジ・ダハーカ、etc |
| 宿敵 | 善神アフラ・マズダー (スプンタ・マンユ) |
そもそもゾロアスター教とは?

まずはアーリマンの解説の前に、アーリマンが登場するゾロアスター教の特徴を簡単に。
ゾロアスター教とは、その名の通りゾロアスター(ツァラトゥストラ)を開祖とし、紀元前2000年代に古代ペルシャ近辺で発生したとされる宗教です。その歴史は非常に古く、キリスト教やイスラム教などの原型になったとも言われているほか、ササン朝ペルシアでは国教として扱われていたことなどが歴史上に記録されており、それだけでも世界の文明に影響を与えたことは読み取ることができます。
ゾロアスター教はイスラム教などと同様に、偶像崇拝を行わない宗教であり、信者たちは善や光の象徴として、神殿の中にある”火”に向かって礼拝を行ないます。このため、ゾロアスター教は別名として「拝火教」とも呼ばれています。
現在では信徒が非常に少なくなり、全世界的に見ても信者の数は10万人ほど。それに伴い日本ではほとんど見られなくなった宗教ではありますが、インドやイランといった東南アジアや中東圏、あるいは欧米諸国には根強く信仰を持ち続ける方々も存在しており、ゾロアスター教の教えは今も世界の中に受け継がれているのです。
そして、ゾロアスター教の教義における大きな特徴にはもう一つ「善悪二元論」という認識が存在しています。善神であるアフラ・マズダーと悪神であるアーリマンの対立が世界の創世に繋がっていることからも伺い知れる特徴ですが、これについては次以降のトピックで、アーリマンの側面から解説していきたいと思います。
アーリマン(アンリマユ)は「悪」を選択した神

アーリマンという存在を一言で表すには、やはり「絶対悪」という言葉を使うしかありません。
アーリマンはゾロアスター教の創世神話において、アフラ・マズダーと並ぶ創造神であり、世界の原理として「悪」を選択した神であるとされています。そのためゾロアスター教においては、「人に利をもたらすもの=善神であるアフラ・マズダーの被造物」、「人に害をもたらすもの=悪神であるアーリマンの被造物」として語られているのです。
そして、世界が始まる前に出会ったアーリマンとアフラ・マズダー(神話成立当初はスプンタ・マンユ)は世界の原理や構成を巡る激しい戦いを繰り広げ、その末にアフラ・マズダーが勝利。敗北したアーリマンはアフラ・マズダーによって深闇に落とされたとされています。
しかしアーリマンは現在も深闇の中で勢力を盛り返しながら生存しており、世界の終末において再びアフラ・マズダーと戦うことが宿命づけられているとか。キリスト教の終末論にも似たようなことが書かれている辺り、やはりキリスト教の原型である部分が感じられますね。
アーリマン(アンリマユ)の化身はヘビ!?

アーリマンが登場するゾロアスター教には偶像が存在していないため、一般的な「こういう姿」という形でアフラ・マズダーやアーリマンの姿を知ることはできません。しかしその一方で、アフラ・マズダーの象徴に”火”が使われているように、”象徴”という形で神々の特性を知ることはできます。
アーリマンの場合、その神格を象徴するのは”蛇”や”トカゲ”などだと言われています。その特徴は、アーリマンが生み出した怪獣「アジ・ダハーカ」の物語にも色濃く表れており、アーリマンやその眷属の象徴、あるいは化身としては、蛇やトカゲなどの爬虫類、あるいは毒虫や猛獣などの人に害を成す生物が一般的です。
キリスト教ではアダムとイヴをそそのかした存在として描かれる蛇ですが、そういったいわゆる”悪”のイメージと蛇が重なったことには、もしかするとゾロアスター教の影響があったのかもしれません。
アーリマン(アンリマユ)と関わり深い”ダエーワ”とは?

ダエーワというのは、アーリマンの配下である悪神たちの総称です。それぞれが「乾き」「疫病」「不道徳」などの人間に害をなす様々な事物を司っており、アフラ・マズダー率いる善神群と対立関係にある存在として神話の中に描かれています。
ダエーワそれぞれの特徴はまちまちですが「人に害をなす」という部分と「善神の一柱と相関関係にある」ということは共通しています。そういう意味では、キリスト教における「悪魔」と近い存在、あるいはそのモデルだと見ても良いでしょう。
有名なところで言えば、「人に悪しき思考を植え付ける」というダエーワのアカ・マナフの場合。それと相関関係にあるのは「人の良い思考を司る」という善神(アムシャ・スプンタ)のウォフ・マナフであり、司るものからして明らかな対比構造が生じています。
他にも、「無秩序」のダエーワであるサルワに対する「秩序」の善神・フシャスラ・ワルヤ。「熱」のダエーワであるタルウィに対する「水」の善神・ハルワタートなど、ゾロアスター教の神話には各所に相関や対立の関係が見えています。こういう部分も、ゾロアスター教の特徴である「善悪二元論」を象徴していると言えるのではないでしょうか。
しかし実はこの「ダエーワ」という存在。ゾロアスター教の視点から見ると悪神なのですが、とある別の神話の視点から見てみると……という面白い構造になっています。この構造については、次のトピックにて説明していきますのでご一読ください。
アーリマン(アンリマユ)にまつわる神話・逸話
神話・逸話1「インド神話とも関係している?」
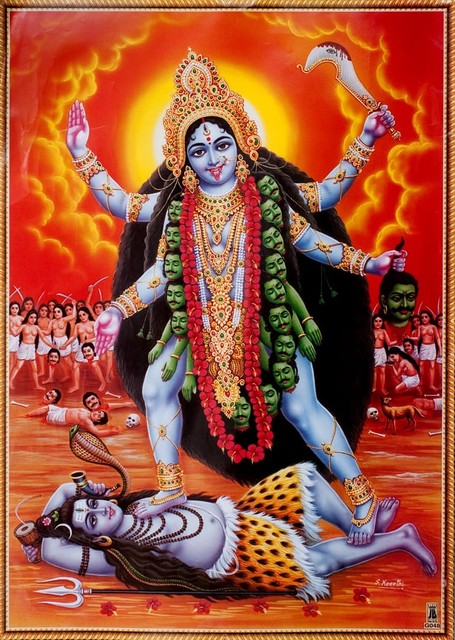
「現存する世界最古の宗教」としても名高いゾロアスター教ですがそこに語られる神話にはある特徴があります。実はゾロアスター教の創世神話は、おそらく同時期に成立しただろうと目されるインド神話と、興味深い相関関係になっているのです。
例えば、インド神話においては破壊と創造を司る神として信仰を集めるシヴァ神が、ゾロアスター教の中ではサルワというダエーワ――つまり、アーリマンの配下である悪神として描かれていたり、インド神話においては悪神であるアスラが、ゾロアスター教の中では善の最高神アフラ・マズダーだったりと、おそらく意図的だと思わしき善悪の相関関係が随所に見られるのが、ゾロアスター教の創世神話とインド神話の大きな特徴になっているのです。
互いの神話成立当時の記録はほぼ残っておらず、当時の神話編纂者や国同士で何が起こったのかは不明ですが、意図的でなければありえないこのような事態が起こるあたり、明らかに意識的にお互いの奉じる神を扱っているように思えます。
当時の様々な情勢などを想像し、そこから成立した神話の本義を考察してみても、興味深い結果になるかもしれませんね。
神話・逸話2「数ある神話中でも最強レベルの”魔王”」

世界には様々な神話が存在しており、その中には時として「設定盛りすぎじゃない?」と思えるような神格もかなりの数存在しています。それこそ、前述のインド神話におけるシヴァ神などは「破壊と創造」という相反するものを司る時点でその典型だと言えるでしょう。
しかしそういった観点からすると、アーリマンもそういった「設定の盛られた」神格であると言えます。というよりむしろ、アーリマン以上に範囲の広い神格はそうそう存在しません。
創造神であり悪神。人間に対する試練をいくつも創造し、善に対する悪を貫き通す存在として描かれているアーリマンは、「人間の敵」という面ではサタンなどの悪魔と同一ですが、それ以上に広い範囲を司っている、まさに「魔王の中の魔王」と呼べるような存在なのではないでしょうか。
そして、そんな神話を元にしたはずの別の神話では、アーリマン程の「絶対悪」という存在が描かれていないことも興味深い部分です。ゾロアスター教創世神話から、キリスト教、イスラム教などに至るまでにどういった変化が起こったのか。考察してみても面白いかもしれません。
![レキシル[Rekisiru]](https://rekisiru.com/wp-content/uploads/2021/04/Rekisiru_Logo_v3-1.png)