日本美術史とはその名の通り、日本の美術の歴史のことです。それでは解説していきます。
この記事を書いた人
一橋大卒 歴史学専攻
Rekisiru編集部、京藤 一葉(きょうとういちよう)。一橋大学にて大学院含め6年間歴史学を研究。専攻は世界史の近代〜現代。卒業後は出版業界に就職。世界史・日本史含め多岐に渡る編集業務に従事。その後、結婚を境に地方移住し、現在はWebメディアで編集者に従事。
日本美術史の魅力
日本美術史の魅力は何でしょうか?複雑なことは抜きにして筆者の考える魅力をまとめます。
1. 美術史を通して日本史を知ることができる

西洋美術史などでは主に絵画や彫刻を美術史としてまとめることが多いですが日本美術史はそれらに加え工芸品や書、建築なども美術史として挙げることが多いです。
美術史と呼ベるジャンルが多い分、作品ができた時代背景や時代の流行を知ることができ日本の歴史を知る上でとても有効に活用できると思います。
日本は2000年を超える美術の歴史があるといわれており、世界と比べても引けを取らないです。歴史が長くなればなるほど情報源は少なくなりますが絵画をはじめ美術品が発見されることによって我々はより確かな歴史をたどることができ、後世に記録を残すことができるのです。
日本独自の美術観はもちろん、日本の歴史に触れることができるのも1つの魅力ですね。
2. その美術品ができた背景から作品の見方が変わる
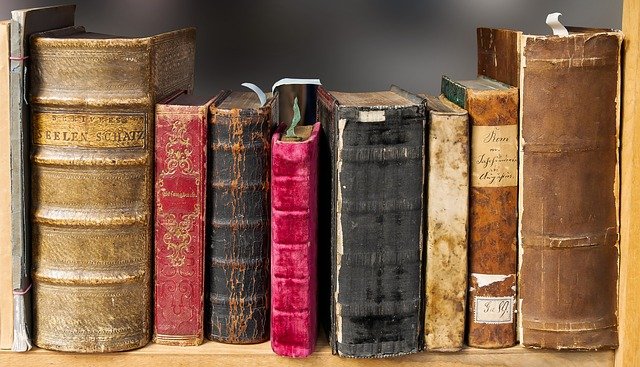
現代人の我々は何をするにも便利な道具があります。しかし遥か2000年前にはもちろん道具などはなく自分たちで創作しなければなりません。
なぜ縄文土器ができたのか、なぜ仏像が作られたのか。そこには確かに美術品を作らなければならなかった、もしくは作るべきだった理由があります。
その理由を知ることでより深く美術品を鑑賞することができ、当時の人々が考えていた想いを知ることができるのではと考えます。1つの目線だけでなく多方面から考えることでまた新たな美術史の魅力に気づけるのではないでしょうか。
日本美術史の略歴年表
弥生時代の土器は煮炊きのほか、保存するためや食べ物を盛るためとしても使われており縄文土器よりもシンプルに作られています。
またこのころから中国大陸との交流が始まり、青銅器などが流通しました。とくに銅鐸は日本でさらに発展し次第に祭器となり、所有者の権威を表すものにもなりました。
古墳時代から権力争いが盛んになり、王権ができはじめます。それが分かる代表的なものが前方後円墳です。そしてその古墳上にあるのが動物の形や人間の形をした埴輪です。
服装や髪型などがリアルに表現されているためその時代の生活を知ることができる貴重な美術品になっています。
時代が変わるとさらに仏教は広がり寺院を建立、仏像を像立するなど国家の事業となりました。この時代は大きく分けて白鳳時代と天平時代に分けられ、特に天平時代は名前から天平文化と呼ばれ絵因果経や正倉院宝物などがあります。
多くの美術品が作られた時代でありながらも天災や凶作に見舞われることも多かった時代です。
最澄・空海が唐に渡ったことで外国の文化の影響をより受け密教曼荼羅や密教彫像が造られました。
その一方で外国の文化を受けながらも日本ならではの文化にも変化していき、仮名文字ができるなど和風化した面もあります。仮名文字を使った代表的な書物といえば源氏物語や枕草子などがあります。
足利義満によって金閣寺を、足利義政が銀閣寺を造り和の文化がさらに発展した時代です。そして美術の分野において影響が大きくあったのは禅宗が伝来したことです。書道や水墨画、日本庭園、華道など日本文化とされる美術は禅宗から始まったとされています。
日本の住宅建造に大きな影響を与えた書院造や現代でも日本伝統として受け継がれてきている能も観阿弥・世阿弥によって室町時代に創られました。
美術では特に絵画や建築、茶の発展が著しい時代でした。庶民の日常生活を親しみやすい画風で描いている風俗画や城のシンボルとして造られた天守閣、さらに千利休によってわび茶という茶の湯が完成したとされています。
19世紀中頃にヨーロッパの万博博覧会に美術品として出展された作品が西洋に高く評価され、このことをジャポニズムと呼ぶようになりました。有名な画家ゴッホやクロード・モネなどもジャポニズムの影響を受けたとされる作品があります。
西洋美術が雑誌で紹介されたことをきっかけに20世紀初頭に始まったフォーヴィズムやキュビズムなどが支持され自由な表現、個性を出す絵画が多く生まれた時代です。しかし昭和期に入ると自由を制限、弾圧されることが増えていき次第に戦争画を描くことで戦争に協力する形となっていきました。
現代でも大阪のシンボルとなっている岡本太郎作品の太陽の塔やその対となる明日の神話もこの時代に作られています。
![レキシル[Rekisiru]](https://rekisiru.com/wp-content/uploads/2021/04/Rekisiru_Logo_v3-1.png)
あいう球