島崎藤村は明治後期から昭和初期にかけて活躍した詩人・小説家です。「夜明け前」や「破戒」等の作品名は耳にした事があるかもしれません。藤村の作品は自分自身の壮絶な経験をもとに作られており、大きな反響を呼びました。これらの作品は「自然主義文学」と呼ばれています。
藤村の作品が文学界に与えた影響は大きく、「社会の矛盾や人間の欲望等、思わず目を背けてしまうようなリアリズムを追求する作品」が後に生み出されています。「人間の本質」を探求したい人に是非とも読んで欲しいですね。

ただ藤村の私生活を覗き見ると、「教え子や姪との禁断の恋」「子供を置いて海外に留学する」等、非常に破天荒な生活を送っています。藤村は決して高尚な人間ではなく、その生き様を批判される事もあったのです。ただそんな人間だからこそ、作品に重みが生まれ、自然主義文学というジャンルを開拓出来たのかもしれません。
私は幕末の人間群像を描いた「夜明け前」を読み、藤村の作品の虜になりました。その後は藤村の作品を図書館で読み漁った事を覚えています。今回はそんな筆者が、島崎藤村の生涯について解説していきます。
この記事を書いた人
Webライター
Webライター、吉本大輝(よしもとだいき)。幕末の日本を描いた名作「風雲児たち」に夢中になり、日本史全般へ興味を持つ。日本史の研究歴は16年で、これまで80本以上の歴史にまつわる記事を執筆。現在は本業や育児の傍ら、週2冊のペースで歴史の本を読みつつ、歴史メディアのライターや歴史系YouTubeの構成者として活動中。
島崎藤村とはどんな人物か
| 名前 | 島崎藤村 |
|---|---|
| 誕生日 | 1872年3月25日 |
| 没日 | 1943年8月22日 |
| 生地 | 筑摩県馬籠村(現在の長野県中津川市) |
| 没地 | 神奈川県大磯町 |
| 配偶者 | 秦冬子(前妻)・後妻(静子) |
| 埋葬場所 | 地福寺(神奈川県大磯町)・永昌寺(岐阜県中津川市) |
島崎藤村の生涯をダイジェスト
島崎藤村の生涯をダイジェストすると以下のようになります。
- 1872年 0歳 島崎藤村誕生
- 1886年 14歳 父・正樹死去
- 1892年 20歳 明治女学校の教師となる
- 1893年 21歳 北村透谷らと「文学界」を創刊
- 1896年 24歳 母・縫死去 この頃から詩作を開始
- 1906年 34歳 破戒の自費出版
- 1913年 41歳 姪のこま子と関係を持つ
- 1818年 46歳 新生を新聞に掲載
- 1929年 57歳 夜明け前を連載
- 1935年 63歳 日本ペンクラブの初代会長に就任
- 1941年 69歳 神奈川県大磯町に転居
- 1943年 71歳 大磯町の自宅で死去
詩人から小説家へと転向し、「破戒」を執筆
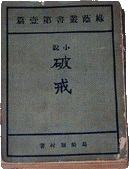
藤村は1906年に「破戒」を自費出版しています。内容は以下の通りです。
主人公の瀬川丑松は被差別部落出身で、その事をひた隠しにして生きてきました。小学校教師となった丑松は、被差別部落出身の活動家の猪子蓮太郎を慕い、自分の出生を猪子になら打ち明けても良いと考えます。
結局丑松は出生を伝えられず、月日だけが流れます。ある日「丑松が被差別部落出身」という噂が流れ、同時期に猪子が壮絶な死を遂げました。追い詰められた丑松は子供達に自分の出生を告白。丑松はテキサスへ旅立つという内容です。
破戒の意味は「被差別部落出身である事は誰にも言うな」という父の「戒めを破った」事が由来です。後に全国水平社が部落解放運動を展開する中で、丑松が「部落民である事を隠していた事を謝る」という点が問題視されます。
差別的な言葉を廃絶しようとする時流の中で、破戒は一度絶版となりました。その後「進歩的啓発の効果」という目的で破戒が復刻される等、後々まで破戒が社会に与えた影響は大きかったのです。
近代文学を代表する作品「夜明け前」を執筆

小説家として不動の地位を築いた藤村は、1929〜1935年の間に「夜明け前」を中央公論にて連載します。その質の高さから、日本の近代文学を代表する小説と評されています。内容は以下の通りです。
舞台は1853〜1886年。黒船来航から明治維新を経て、近代日本が形作られていく時期です。主人公は中山道木曾馬籠宿で庄屋を営みつつ、国学に傾倒する青山半蔵。
半蔵は明治維新に期待を抱くものの、待っていたのは西洋文化を意識した文明開化、国民への更なる圧迫でした。半蔵は精神を蝕まれ、寺への放火未遂事件を起こします。半蔵は座敷牢に閉じ込められ、廃人となり病死しました。
青山半蔵のモデルは、役人となるものの後に発狂して獄中死した島崎正樹。藤村の父親です。歴史とは時の権力者の視点から見たものが語られますが、藤村は庶民の目線から幕末から明治という激動の時代を執筆したのです。

例えば夜明け前第1部では、和宮が徳川家茂の元へ嫁ぐ際に中山道を通る様子が描かれています。和宮一行が通り過ぎた後には、「沢山の死体が転がっていた」そうです。
これらの描写は夜明け前には記載があるものの、徳川幕府の記録にはありません。婚礼の儀式の際に死体や血を見る事は「忌み事」になる為、あえて記録には残さなかったと思われます。
夜明け前は作品の質は当然の事、徳川幕府が記録として残せなかった事も書かれています。夜明け前は資料的価値を見出す事の出来る作品なのです。
島崎藤村の家族構成は?8人の子と2人の妻がいた
藤村は1899年に秦冬子と結婚します。藤村が「破戒」の執筆を開始した頃です。1900〜1904年の間に3人の娘が生まれますが、当時の藤村は執筆に明け暮れていました。3人の子供を食べさせる為、秦冬子は懸命に働きました。
1906年3月に破戒を自費出版。この前後に3人の娘を栄養失調でなくしています。その後は1905〜1910年に3人の息子と1人の娘を授かるものの、四女の柳子を出産した際に秦冬子は亡くなります。
藤村は1928年に加藤静子と再婚。藤村が56歳の頃でした。1924年に藤村は静子にプロポーズをしており、手紙で思いを以下のように伝えています。
わたしたちのLifeを一つにするといふことに心から御賛成下さるでせうか。それともこのまゝの友情を―唯このまゝ続けたいと御考へでせうか
藤村は結婚という言葉ではなく、LIFEを1つにすると書きました。これは日常生活だけではなく、文学の創作なども含めて生き方の全てを共にしたいという思いが込められています。
このプロポーズから4年後に2人は結婚。翌年には日本文学の金字塔である「夜明け前」が中央公論に掲載されました。この執筆の過程には静子の献身的な支えがあった事は間違いありません。
静子はその後も藤村とLIFEを1つに暮らします。藤村死去後も1973年まで存命でした。
藤村は姪のこま子と関係を持っていた?

藤村は兄広助の次女である島崎こま子とただならぬ関係にありました。きっかけは秦冬子が出産後に死去し、こま子が藤村の家の手伝いをする為に訪れる機会が増えた事にあります。
1912年頃から藤村とこま子は愛人関係となり、やがてこま子は藤村の子を身籠もります。藤村は子どもを受け入れる事なく、こま子や幼い子どもを残してバリへ留学するのです。2人の子は里親に出されています。
1916年に帰国した藤村は、再度こま子と関係を持ちました。1918年に発表された「新生」は禁じられた関係を清算する為に作られたものだったのです。
「新生のモデルはこま子である」という事が明るみに出ると、こま子は日本に居場所がなくなり、伯父秀雄のいる台湾に移住。その後1919年に日本に戻り、社会主義の活動をする等して、1979年に死去しています。
![レキシル[Rekisiru]](https://rekisiru.com/wp-content/uploads/2021/04/Rekisiru_Logo_v3-1.png)